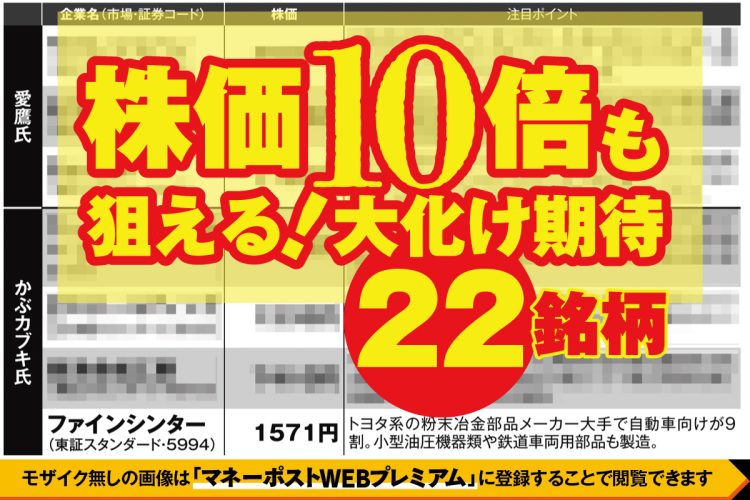しかしながら、18歳人口が激減する中で、パイの縮小を遅らせたり、18歳人口の減少の影響はないような姿勢をとり続けたりしたところで、問題が解決するわけではない。
新学部の設置だけでなく、大学名や学部名を変えるイメージチェンジを図る動きも相次いだが、目先の改革をもって18歳人口を奪い合ってみても、展望は開けない。すべての大学に十分な数の入学者は行き渡らないのである。
それどころか、18歳人口が激減する状況下でのパイの奪い合いは、人気上位校への偏在を進める。そうではない多くの大学にとっては破綻を早める結果に終わろう。拡大のために投資した額が回収できないうちに事業継続ができなくなろうものなら、負債額は巨大なものになる。
■後編記事:【大学2026年問題】国立大学すら定員割れは時間の問題…文科省も「大学じまい」に舵を切ったが、そのタイミングはあまりに遅すぎた
【プロフィール】
河合雅司(かわい・まさし)/1963年、名古屋市生まれの作家・ジャーナリスト。人口減少対策総合研究所理事長、高知大学客員教授、大正大学客員教授、産経新聞社客員論説委員のほか、厚生労働省や人事院など政府の有識者会議委員も務める。中央大学卒業。ベストセラー『未来の年表』シリーズ(講談社現代新書)など著書多数。話題の新書『縮んで勝つ 人口減少日本の活路』(小学館新書)では、「今後100年で日本人人口が8割減少する」という“不都合な現実”を指摘した上で、人口減少を前提とした社会への作り替えを提言している。