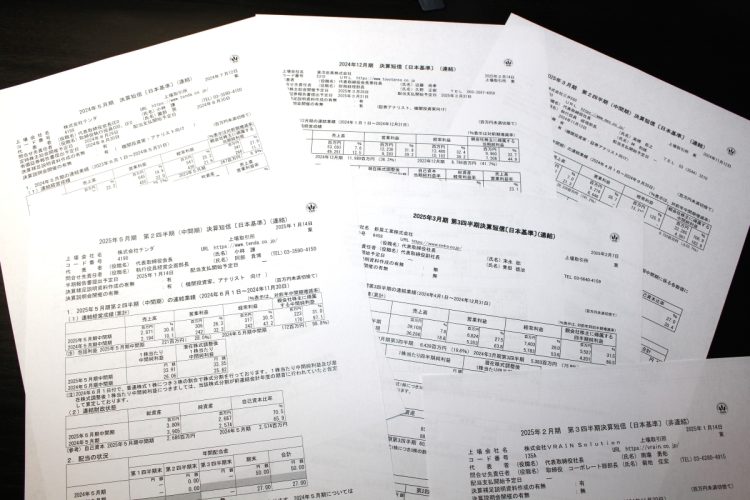「ケンタッキーフライドチキン」の創業者カーネル・サンダースは日本KFCの味を高く評価した
「ケンタッキーフライドチキン」を運営する日本KFCホールディングスが、三菱商事傘下を離れ、米投資ファンドカーライル・グループに買収された。同社は9月中に上場廃止となり、新たな出発をすることになる。カーライルは買収後、「積極的な出店戦略」や「メニューの多様化などによる売上の成長加速」「デジタルの強化」などを進めるとする。
その一方、同社が守り続けた「伝統の味」が変わってしまうのではとの不安の声も多くある。1970年に日本1号店がオープンして以降、同社が「味」にこだわり続けた背景には、創業者のカーネル・サンダース氏から直接託された「願い」があった──。