パンダがつないだ日本と中国の歴史を振り返る(上野動物園で2018年に撮影されたシャンシャン。共同通信社)
白と黒のツートンカラー、ずんぐりむっくりとした体型。こちらを見つめるつぶらな瞳。その唯一無二の愛らしい動物は、いまから約50年前に海を渡ってやってきた。その系譜と足跡を振り返ると、決して「かわいい」だけの存在ではないことがわかってくる──。《特集「パンダがつないだ日本と中国の50年史」全文公開》
パンダがつないだ日本と中国の歴史を振り返る(上野動物園で2018年に撮影されたシャンシャン。共同通信社)
白と黒のツートンカラー、ずんぐりむっくりとした体型。こちらを見つめるつぶらな瞳。その唯一無二の愛らしい動物は、いまから約50年前に海を渡ってやってきた。その系譜と足跡を振り返ると、決して「かわいい」だけの存在ではないことがわかってくる──。《特集「パンダがつないだ日本と中国の50年史」全文公開》






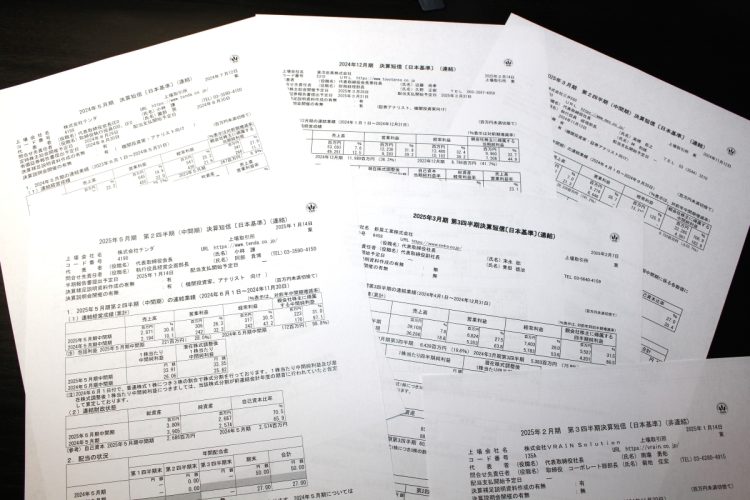




当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。