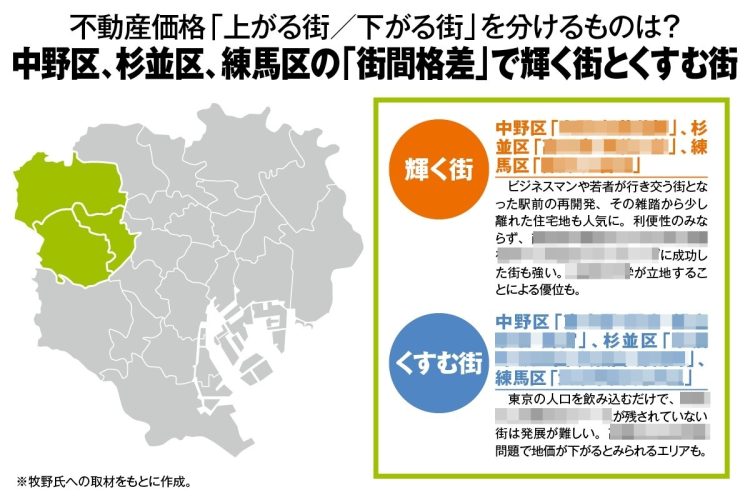生き続ける「市場原理主義」の残酷
では経済学者がさかんに宣伝した経済的自由主義とはなんぞやである。簡単に要約すると、経済活動ではその最大限を個人に委ねるべし、と主張する考え方だ。つまり、国家は介入するな、ほったらかしにしておけ、である。多少の混乱はあるかもしれないが、やがて市場がよきに計らってくれるのだから、下手な手出しは無用、信頼すべきものは国ではなくて市場だというわけである。
この市場原理主義は古典派経済学の基盤になっている。古典派といっても古くてオワコンだというわけではなく、むしろこちらのほうがいまなお主流であり主流派経済学とも呼ばれる。この考え方はアダム・スミスの時代から綿々と続いていて、その強靭さはときに非常に残酷である。
1845年、アイルランドはジャガイモが凶作で大飢饉に見舞われた。1801年以来、アイルランドを統治していたのはイギリスだった。当時のアイルランド人の主食はジャガイモだった(小麦はイギリスに搾り取られていた)ので、そのジャガイモが伝染病で凶作に見舞われたのだから大変だ。当然、連合王国を主張していたイギリス政府はアイルランド人を救済しなければならない、——とまぁ普通は考える。しかしこの時、「そんなことをするべきではない。ほったらかしにしておけ」という社説がエコノミクス誌に載った。
なぜか? もちろんそれは、政府は市場に手を出すなという市場原理主義に抵触するからである。また、一度そんなことをしてしまえば、アイルランド人を甘やかすことになり、彼らは今後も国からの援助に頼るようになるだろう(モラルハザードの問題)、というわけだ。結果、この論は受け入れられ、2年連続で凶作になったアイルランドでは、数十万人の餓死者が出たと言われている。自由放任政策が生んだ死者である。自由放任はフランス語でレッセフェール(なすに任せよ)と言うが、語感からしてビートルズの「レットイットビー」を連想してしまい、ファンの僕としては居心地が悪い。
経済学者は今も銀行の味方なのか
ときは流れて2008年、リーマン・ショックが起こったときに、政府は市場原理主義に任せて、銀行が崩壊するのを黙って見ていただろうか。答えはNOである。「大きすぎて潰せない」という理由で、銀行の延命策が図られ、多くの資金が投入された。さて、このときも古典派経済学者らは毅然として立ち上がり、市場に任せろ、政府は余計なことをするな、潰れる銀行は潰させろとスクラムを組んでキャンペーンを張ったかと言うと、そういうことは聞かない。だからひねくれ者はこう考える。経済学者というのはやはり銀行家の味方ではないか、と。
もちろん、意図的に意地悪な言い方をしていることは自覚している。そもそも1845年と2008年では人権に対する考え方がまったくちがうという反論も承知の上だ。けれど、2008年の金融危機に際して、アメリカ政府がGDPの4.5%にあたる資金を、イギリス政府は8.8%を銀行救済に使ったことは事実だ(『21世紀の貨幣論』フェリックス・マーティン)。「大きすぎて潰せない」という理由もないではないが、ちょっと考えて欲しい。金融商品を買ったり売ったりしていたのは、おしなべて言えば、金銭的に余裕のある層と銀行だ。それなのに、金融市場のカジノには一切足を踏み入れたことのない国民から吸い上げた税金を湯水の如く使って銀行を救済したことを、不平等だと感じるなというのは無理がある。