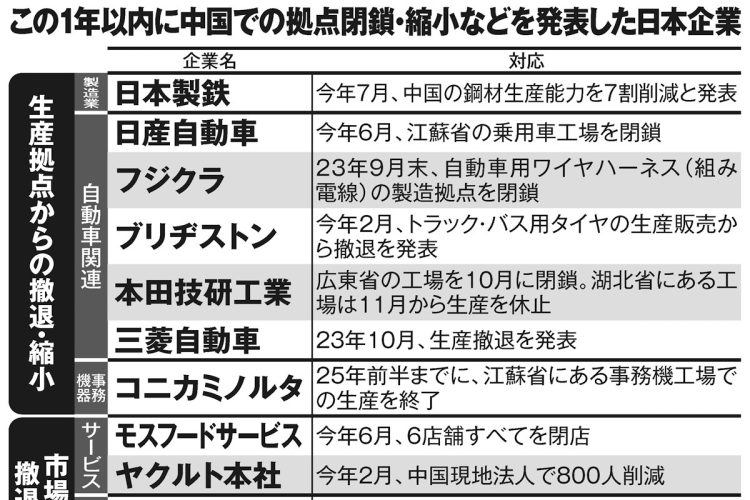株式市場は高値を更新(写真は11月17日。時事通信フォト)
米大統領選挙は大接戦の末、ようやく民主党のジョー・バイデン氏の勝利が確実となったことを受けて、日経平均株価はバブル崩壊後の1991年以来、実に29年ぶりとなる高値を更新した。果たしてこの先は、どのような展開となるのだろうか。カブ知恵代表の藤井英敏氏が、株式市場の先行きを読み解く。
* * *
日米で国のトップが交代し、市場は連日の株高に沸いている。だが、トップが誰になろうとも、今後も株高トレンドは続くのではないか、と見ている。その最大の理由は、各国の中央銀行がこれまで行なってきた大規模な金融緩和を、新型コロナウイルスの景気対策として続けざるを得ないからだ。金融緩和とは、市場に出回るお金の量を増やして景気を上向かせようとすること。世界中の中央銀行が、輪転機を回して紙幣をばら撒くように資金供給量を増やし続ける限り、株式市場への資金流入も止まらないだろう。
もちろん、全面的に一本調子で上がり続けるわけではない。コロナの感染拡大が進むなか、これまでは巣ごもり需要を背景に業績を拡大してきた米国の巨大IT企業「GAFAM」(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフト)を中心とした「グロース株(成長株)」がこぞって買われてきた。
ところが、米ファイザーが11月9日、開発中のコロナワクチンの治験で「90%を超える有効性が確認された」と発表すると、「コロナが近いうちに収束に向かい、景気も回復するのではないか」という投資家の期待が高まり、相場は一変。それまでコロナ禍で売り込まれていた航空や旅行関連などの「景気敏感株」が一気に買い戻され、構成銘柄に景気敏感株を多く含むNYダウが急騰した。反対に、それまで買いが集中していたGAFAMなどのハイテク株中心のナスダック総合指数の上昇は一服した。
米国との連動性が高い日本株市場でも同様の動きが見られた。景気敏感株の上昇によって、日経平均株価は29年ぶりの最高値を更新して上昇する一方で、コロナ禍で堅調だった巣ごもり消費関連銘柄を多く扱う東証マザーズ指数は下落。日米ともに、「グロース株」一辺倒から「バリュー株(割安株)」を見直す動きへとシフトしているのだ。