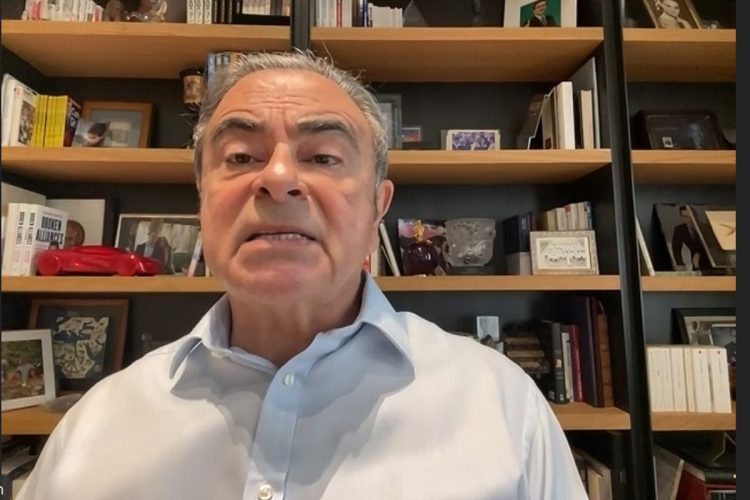女性が働くようになったのは女性活躍推進の政策のおかげではない(写真:時事通信フォト)
菅義偉官房長官は2018年12月の記者会見で、「ジェンダー・ギャップ指数」の順位が日本は149か国中、110位と極めて低いことについて、「この5年間で女性の就業者数は201万人増えている」と述べ、政権が取り組む女性活躍推進の成果を強調した。しかし、本当にそうだろうか。
『アンダークラス』(ちくま新書)の著者で、社会学者の橋本健二さん(早稲田大学人間科学学術院教授)が説明する。
「端的に言えば、女性の就業者数が増えたのは、政府の労働政策の結果ではありません。女性は、“稼がなければ生活できない”という必要に迫られて働いているに過ぎません。
高度経済成長期の日本の景気は安定して上向きで、『一億総中流社会』でした。そのため、多くの場合、女性は働かなくても夫の稼ぎだけで生活できた。しかし、1970年代のオイルショックを機に雇用が低迷、徐々に格差が拡大し始めます。
バブル崩壊を経て、大部分の人は収入が低迷し、夫が働けば家族が食べていける時代は終わりを告げました。未婚女性や離死別女性が増加したこともあり、多くの女性は外に出て働かなければ生活できなくなりましたが、その多くは低賃金の非正規労働者で、今や非正規労働者は女性の56%にも達しました」
1990年代後半には、家計の不足を埋めるべく妻が働きに出たため、共働き世帯が専業主婦世帯を上回った。以降、共働き世帯は増加の一途を辿っているものの、世帯あたりの月の可処分所得は、ピーク時の1997年から約7万円も下落。共働き世帯の増加とは対照的に、収入は減少の一途を辿っているのだ。
転職サイト「エン・ジャパン」のアンケート調査によると、大半の女性が仕事をする理由に「家計のため」と答えた。女性が働くようになったのは家計を支えるためであり、ポジティブな社会参加ではなかったのだ。
※女性セブン2019年6月13日号