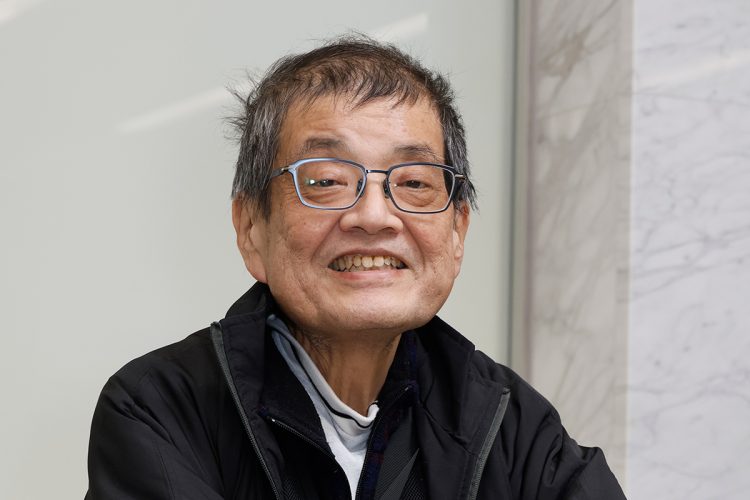私立中高一貫校と公立高校の「国公立大現役進学実績」を比べてみると…(写真:イメージマート)
ブームが過熱するなか、「中学受験しないと取り残されるのではないか」との不安を解消するのは、「公立中→高校受験」ルートについての正しい情報かもしれない。親の世代が高校受験した頃と、今の公立高校はずいぶん様変わりしている。都立高校を例に近年の大学進学実績をみると、私立中高一貫校に引けを取らない学校も多い。そうした都立高校の合格難易度は“レッドオーシャン”と化した「中学受験」と比べてどうなのか。シリーズ「“中学受験神話”に騙されるな」、フリーライターの清水典之氏が、受験情報の専門家への取材を基にレポートする。【第3回】
* * *
小学生の子をもつ親の世代には、通学生徒の居住地を限定する「学区制」の壁に阻まれて、行きたい公立高校に行けなかったという体験をした人もいるのではないか。
学区制だけでなく、東京都や愛知・岐阜・三重の東海3県、福井県には、かつて「学校群制度」(合格者を同じ「学校群」内で振り分ける制度)があり、進学する学校を選べない時代もあった。こうした制度を嫌った学力上位層が公立校を避けるようになり、私立中高一貫校への入学志望者が増えたとの指摘もある。
しかし、現在は少子化の影響で多くの公立高校が定員割れするようになり、学区を維持するのが困難になった地域が増えている。そのため、近年は全国の都道府県で学区制の緩和と高校の統廃合が進んだ。
東京都では、1981年に学校群制度が廃止され、2003年には都内全体が1学区になった。都内に居住していれば、約170校ある都立高校のどこでも受験・入学できる。これにより、かつての都立名門校に学力優秀層が再び集まるようになり、大学進学実績が伸び続けている。