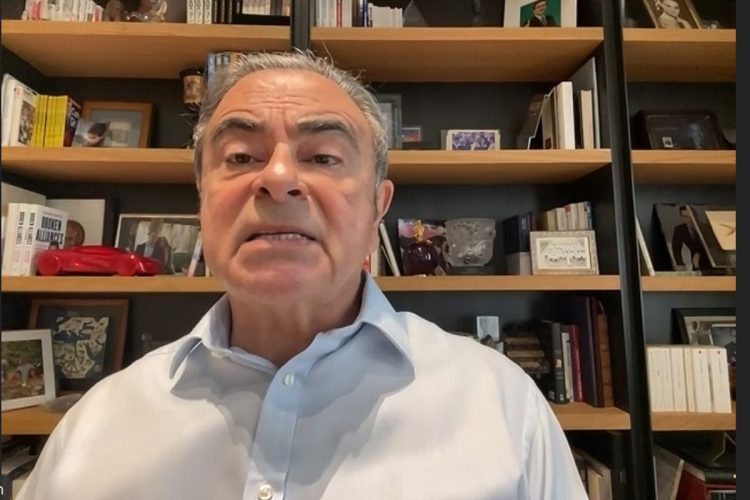「客がいない」と受付女性も嘆く温泉(遊湯センター)
1989年に導入された3%(当時)の消費税は、「高齢化への対応」と「財政再建」のために使われるはずだった。しかし実態は、巨額のカネがホテルや農道空港建設などの公共事業に使われていた。なぜ、「社会保障」の財源が公共事業に化けていったのか。
消費税が創設された平成元年はバブル経済真っ盛り。霞が関では、各省庁が新税の税収を当て込んで全国にスキー場やゴルフ場、マリンリゾートなどを大規模開発する総合保養地域整備法(リゾート法)をはじめ、農道(空港、橋)、スーパー堤防やダム、空港整備計画など巨大事業を用意した。
そこに政治家にとって税収を社会保障や財政再建ではなく、公共投資に回す格好の口実が飛び込んでくる。米国からの「外圧」だった。
折から日米経済摩擦が激化し、時の海部内閣は日米構造協議(1990年)で米国政府から「日本は内需拡大のために毎年GDPの10%(約46兆円)を公共事業に使え」という要求を突きつけられた。国の税収の大半を公共事業にあてなけなければならない、とんでもない金額である。
だが、地元に公共事業をバラ撒きたい自民党の政治家たちは飛びついた。その中心が「自民党のドン」と呼ばれた金丸信・副総裁だ。公共事業に君臨する建設族のボスであり、1988年の消費税国会では、衆院税制特別委員長として消費税法案を成立させた人物でもある。
日米構造協議のさなか、金丸氏から時の橋本龍太郎・蔵相に電話が入る。
「おい、せっかくのアメリカからの要求だ。500兆円くらい出せよ」
ドンの指示だった。