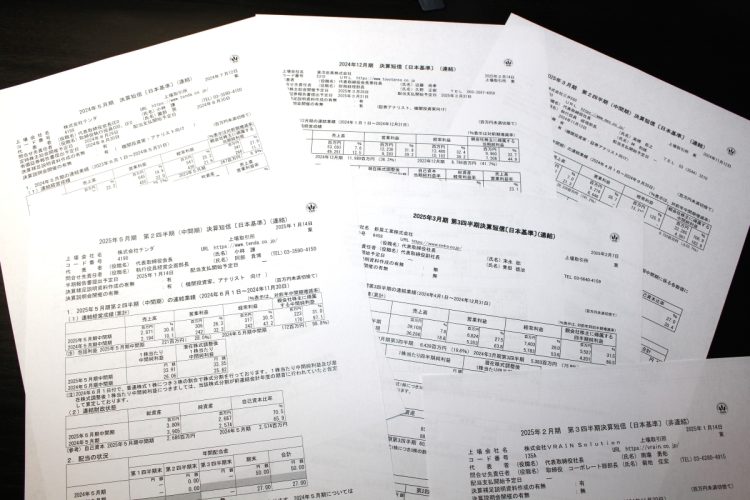定額減税を必死でアピールする岸田首相だが……(時事通信フォト)
岸田文雄・首相は支持率低迷のなか、1人4万円の定額減税のアピールに躍起だ。今月からは企業の給与明細に減税額の明記を義務化した。しかし、その裏では国民にとって大きな負担増につながりかねない議論が進められている。総理大臣が議長を務め、その諮問に応じて内閣の基本方針(骨太の方針)などを議論する「経済財政諮問会議」(5月23日)において、高齢者の定義を現在の「65歳以上」から「70歳以上」に引き上げる提案が行なわれたのだ。実際に引き上げられれば、国民生活に甚大な影響が出る可能性がある。