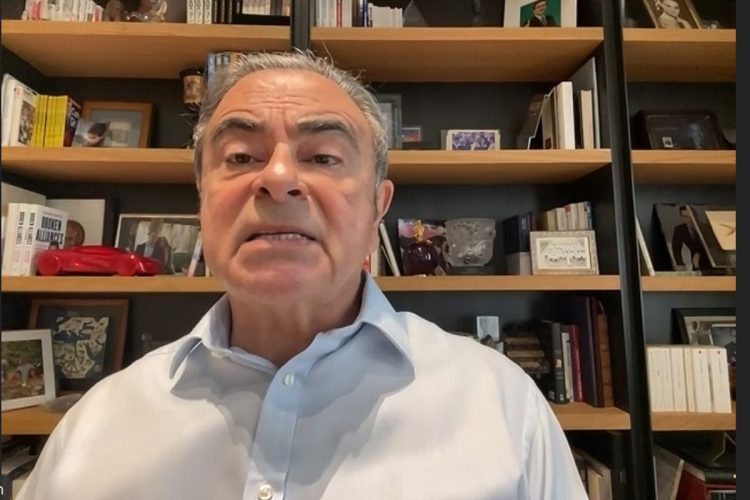YouTubeで見かける機会が増えた緑色のキャラクター「ずんだもん」(C)sss
近頃、YouTubeやニコニコ動画で見かける機会が増えた、ライトグリーンがシンボルカラーで枝豆のような角が生えている、女の子のキャラクター。それが「ずんだもん」だ。動画では、彼女が人工音声でさまざまなジャンルの解説をしており、その内容は歴史や経済、サブカルチャーや雑学まで多岐にわたる。6月下旬時点で、「#ずんだもん」が付いたチャンネルは1.1万、動画数は13万本を超え、なかにはミリオン再生を突破している動画もある。
ずんだもんはどのような経緯で誕生し、どう管理されているのか? ずんだもんコンテンツを手がけるSSS合同会社の代表・小田恭央氏に話を聞いた。
もともとは東北復興のキャラクターとして誕生
「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」のポスター(C)sss
そもそも「ずんだもん」というキャラクターはどのように誕生したのかというと、2011年に起こった東日本大震災後、SSS合同会社による東北応援を目的としたプロジェクトとして始まった。
この「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」では、東北6県の企業や団体に対して、ずんだもんをはじめとする東北にちなんだ12種類の自社キャラクターのイラストを、申請不要・無料で商業利用することを許可している。また個人のクリエイターに対しては、商用目的でない限り、やはり申請不要・無料で利用することが可能となっている。
ずんだもんは、それまではいわゆる“萌えキャラ”のみだったプロジェクト関連キャラクターとの差別化を図り、枝豆をすりつぶした東北の郷土料理「ずんだ」をイメージしたかわいらしい見た目の“人型ゆるキャラ”として公開され、人気を博した(公式設定では「年齢の概念なし」)。
SSS代表の小田氏によれば、ずんだもんが流行りだしたのはコロナ禍に入ってからだという。
「2020年にコロナが感染拡大し始めてから、自宅でコンテンツを楽しむ人が増えたこともあって、自社キャラクターの音声合成ソフトの開発に力を入れたんです。ずんだもんの場合、キャラクターイメージを公開した時点で二次創作が生まれるほど話題となりましたが、音声合成ソフト開発によって生まれたキャッチーな声でさらに話題を集め、認知が広がっていった印象です」
この音声合成ソフトの開発と無料配布によって、ずんだもんは多くの個人クリエイターに利用されていき、現在のようにYouTubeをはじめとするコンテンツに頻繁に登場するようになった。