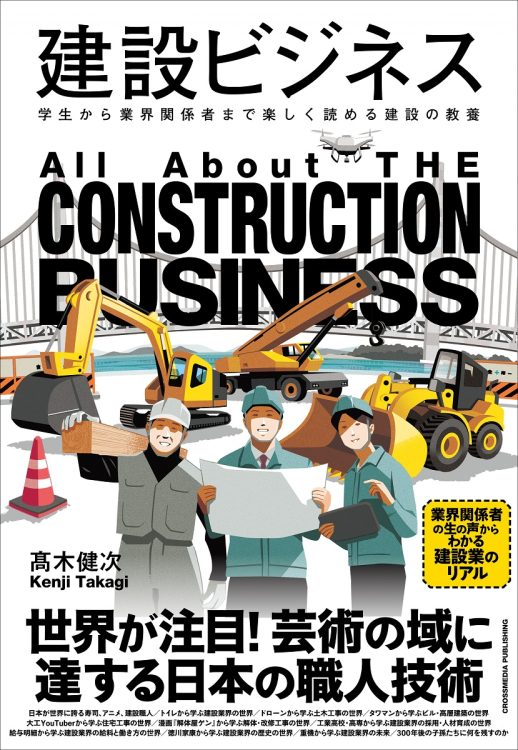公費解体を行うための「法律」のハードル
能登半島地震で8万棟以上の住宅に被害が出た石川県。倒壊家屋のがれきが邪魔で、工事車両が入れないなどの問題が起きています。公費解体は自治体が費用を負担し、所有者に代わって被災家屋の解体などを行う制度です。しかし、2024年9月時点で公費解体が完了したのは申請の16%にとどまっています(石川県発表)。その後、9月の豪雨後に全国から解体業者を集める形で作業班が増強され、急速に公費解体が進みました。
あまり報道されませんが、大きなハードルは「法律」です。家は個人の財産(憲法に定められた個人の財産権)なので、行政の判断だけで「復旧の邪魔だから」と合意なく解体することはできません。被災家屋の公費解体をするためには、行政が一軒ずつ所有者と合意しなければなりません。
では「相続人不明の家」が地震で倒壊したとき、誰が行政と合意するのでしょうか? 建物の所有者が既に死亡し、名義が相続人に変更されていない場合、原則、公費解体に当たって民法上の相続権を持つ全員の同意が必要になります。所有者が亡くなってから時間が経った家の場合、全員の同意を得ることは困難です。そこで環境省と法務省は2024年5月、全壊などで建物の機能が明確に失われた場合、所有者全員の同意がなくても市町村判断で解体できる、という通達を出しています。しかし、一部損壊などの場合は従来通り所有者全員の同意が必要です。
1995年の阪神・淡路大震災以降、日本の災害関連の法律は順次改正されていますが、それでもなお、頻発する災害と相続問題に法律が追い付いていないのです。2024年4月からの法改正で、相続した土地建物の登記(行政への届け出)が義務付けられましたが、我々にできることは法律を確認し「所有者不明の家」を作らないことではないでしょうか。
また、法的なハードルをクリアし、公費解体の工事をする段階になっても、今度は解体工事業者不足が発生します。私が2024年8月に取材した他県の解体工事会社によれば「能登の家屋解体を依頼されても、全く利益が出ないので、大変申し訳ないが断らざるを得ない」とのこと。
※高木健次・著『建設ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)より一部抜粋・再構成
【著者プロフィール】
高木健次(たかぎ・けんじ)/クラフトバンク総研所長・認定事業再生士(CTP)。1985年生まれ。京都大学在学中に実家が営んでいた建設業の倒産を経験。その後、事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。その後、内装工事会社に端を発するスタートアップであるクラフトバンク株式会社に入社。社内では建設業界未経験の新入社員向けのインストラクターも務める。2019年、建設会社の経営者向けに経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、業界団体等での講演、建設会社のコンサルティングなどに従事。
高木健次・著『建設ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)