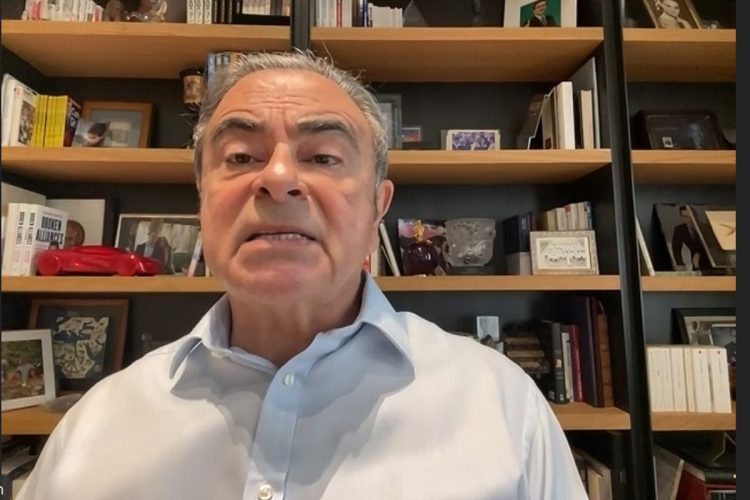「安定している」という感覚が危ない(イメージ)
少子高齢化、労働人口減少が進む現代において「働けば働くほど、人を増やせば増やすほど稼げる」ビジネスモデルには限界がきている――そう指摘するのは、元マイクロソフトで業務執行役員も務めた越川慎司氏だ。現在は、企業成長支援事業を行うクロスリバー代表取締役でもある越川氏は、自身がコンサルティングを担当した経験もふまえながら、この時代に必要なのは“働き方改革”ではなく“稼ぎ方改革”だと提言する。著書『世界の一流は「休日」に何をしているのか』(クロスメディア・パブリッシング)も話題の、越川氏に話を聞いた。
「働けば働くほど売上が上がる」という「労働集約型モデル」に限界
私が上梓した『世界の一流は「休日」に何をしているのか』の中で、上司が休まないと休みにくい会社の特徴の1つとして「長期政権で組織が硬直化している企業」を紹介しました。具体例を挙げれば、「本当は休んで子供の運動会に行きたいけど、上司に嫌われたくないから言い出せない」という空気がある組織です。そのような組織の経営者にはまず、「昔と今は違う」ということを考えていただきたいです。
「労働集約型モデル」という、働けば働くほど、人を増やせば増やすほど売上が上がるというモデルは、工場のラインを回せば売上が上がるという理屈と同じです。今も健在のモデルですが、一方で、生産年齢人口である18歳から65歳までの人口が加速度的に減っていくなかで、そのモデルには限界がきています。
そういう時代に利益を上げるためには、どうやって事業生産性を高めていくかを考えなければならない。しかし、「労働集約型モデル」を取り入れている会社は、裏を返せば「休めば休むほど売上が下がる」という発想のもと、「休み=サボり」という考え方になってしまう。これが問題です。