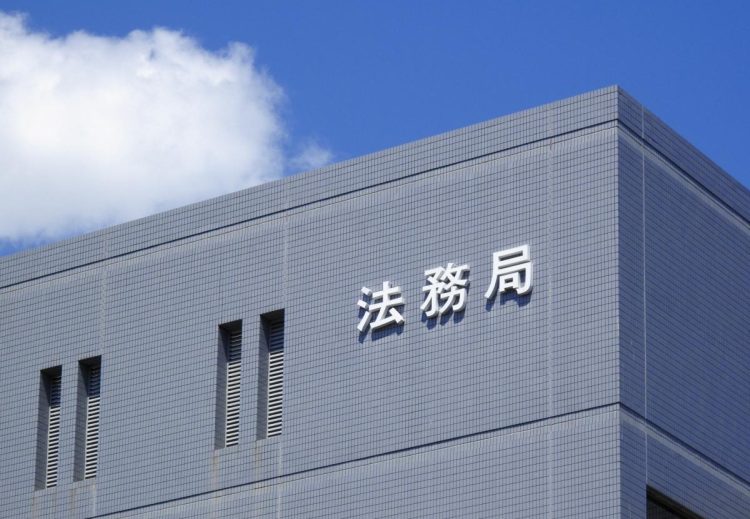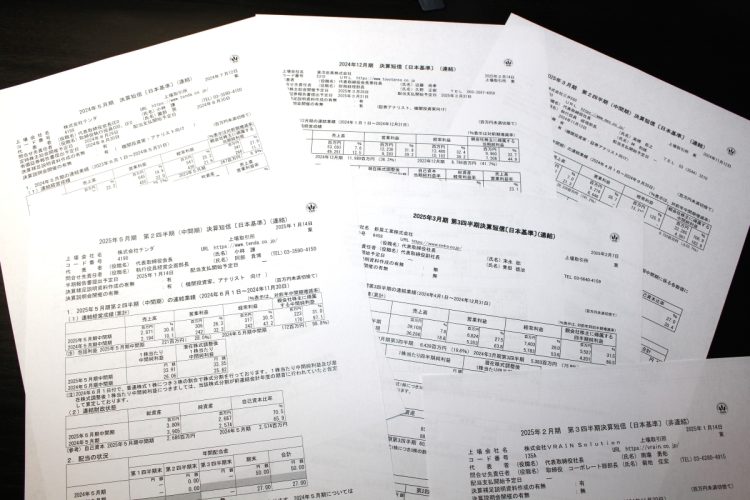相続した実家の登記変更手続きは管轄の「法務局」で行う(写真:イメージマート)
全国で「空き家」が増え続けている。総務省の住宅・土地統計調査の速報集計結果によると、空き家戸数(900万戸)、空き家率(13.8%)ともに過去最高を記録。全国で空き家が増える要因はいくつかあるが、親から相続した家を処分できず、そのまま放置されるケースもあるようだ。地方の田舎で一人暮らしをしていた親を看取ったフリーライター・清水典之氏も、東京に自宅がありながら相続した実家をどうするか悩んでいるという。“想定外”の事態が頻発した「遠距離相続」について、清水氏が綴る。
(全3回の第3回。第1回〈移動距離300km…亡くなった親の銀行口座の凍結解除への長い道のり 最大の難関は「出生から死亡までつながった戸籍謄本」〉から読む)